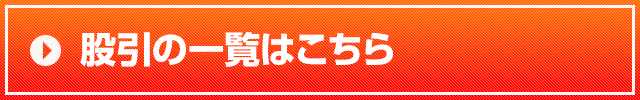股引の折りたたみ方

あまり股引を畳んだフォルムが小さくならないたたみ方を紹介していきます。
小さくまとめるのは片づけやすさがありますが、折り目がたくさん付いてしまうことがあるので注意が必要な面もあるのです。
まず股引を平らなところに広げてください。
股引は前に来る部分に布の合わせ目があり開いているのですが、その面を下にして(お尻の方が上に来るようににして)平らなところに綺麗に広げてください。
綺麗に広げると、腰からお尻あたりから伸びている布が出ているかと思います。
この布が出ている部分の、まずは股引きの左足側を左足の股引きのズボンの上に納まるようにして折り畳んでください。
この時に、股引きの右足側の布に被らないように畳むことが大切です。
股引きの左側が畳めたら次は右足側も同じように畳んでください
。たたむと、シルエット的にはちょうど普段見慣れているズボンのようなシルエットに成るかと思います。
綺麗にズボンの形になっていたら、折りたたんだ布を内側にする世にして左右を真ん中で畳んでください。
そして股引きが半分の形になったら、出ている紐を合わせて畳まれている布を引っ張って形を崩さない様に注意して紐も折畳股引きの上に乗せておいてください。
紐が畳めたら最後に股引をもう一度半分に折って完成です。

- 股引の選び方
- 股引のしまい方
- 股引のたたみ方?
- 股引の折りたたみ方
- 股股引の下にはパンツを履く?
- 股引の下にはふんどしを履く
- 股引の下にはノーパン?
- 股引の作り方は?
- 股引の型紙と作り方は?
- 股引の型紙をとるコツは?
- 股引の色は?
- 股引の色は祭りにより決まるの?
- 股引の色は藍染がいいの?
- 股引のゴム仕様は?
- 股引のストレッチ素材は?
- 晒素材の股引
- 股引のルーツはステテコ?
- 刺子の股引
- 股引のはき方
- 時代劇の股引って?
- 昔の股引は作業用?
- 江戸時代の股引は?
- 太鼓を叩く際の股引って?
- 太鼓を叩く際の藍染股引って?
- 太鼓を叩く際の股引の保管方法
- 股引(ステテコ)の変遷
- ラクダのももひき
- 今どきのももひき
- 和装の股引って?
- 肌着用の股引(和装)
- 和装用股引(ステテコ)
- 股引きとパッチの違いって?
- 股引きの歴史
- 股引の洗い方
- 股引の保存方法
- 祭り以外での使う股引とは?
- 子供・女性用股引
- 女性用の股引
- 人気のある半股引は?
- 男性用の股引
- 半股引って?
- 半股引の洗い方
- 半股引の選び方
- 半股引の歴史とは
- 半股引はいつ履くの?
- 半股引と祭り